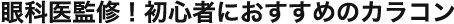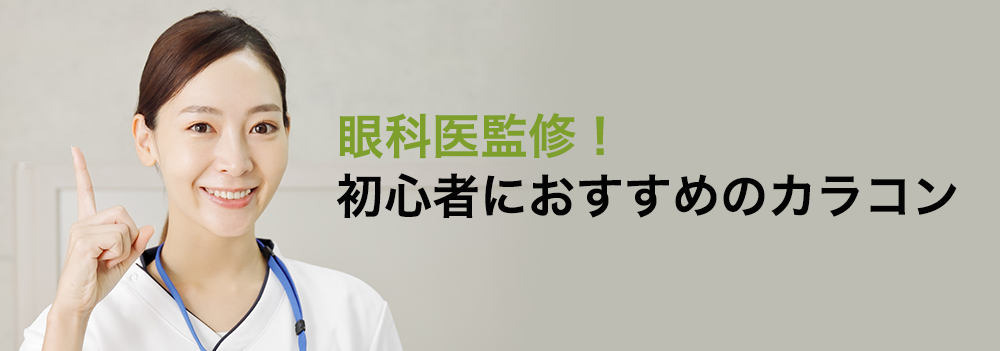乱視用カラコンの特徴は?
乱視とは?
乱視という言葉が聞いたことあるけど、どのような症状かよく分からないという人もいるのではないでしょうか。
角膜などの歪みにより、光の焦点が複数できてしまい、ものが見えにくくなる症状のことを乱視と言います。
ものがぼやけて二重に見えたりすると、目を細めたりすることがありますよね。
そのような場合、乱視の症状が出ている可能性が高いです。
目の疲労が溜まりやすくなったりすることもあり、カラコンを付けるのは危険ではないかと思ってしまうでしょう。
ただ、乱視でも付けられる乱視用カラコンも出てきていますので、安全面を考慮していれさえすれば、楽しくことができます。
乱視用カラコンの選び方
一般のカラコンを選ぶ場合、DIA、着色直径、ベースカーブなどを確認し、適正サイズのものを選ぶのが基本です。
乱視用カラコンを選ぶ場合、どのような数値を確認すればいいのか気になるところでしょう。
乱視の度数と乱視の角度を表す乱視軸の2点を確認すれば、適正な乱視用カラコンを選ぶことができます。
乱視度数はCYLと表記されており、数値が高いほど重度の乱視用です。
乱視軸はAXISと表記されており、0?180度の数値で表されています。
ただ、どちらかの数値が記載されていない製品も少なからず存在しているのが現状です。
両方確認できる製品を選ぶのが無難ではないでしょうか。
長時間の装用はNG!
一般のカラコンを付けるときも、長時間にならないようにと促されていますよね。
乱視用カラコンを付ける人は、乱視の症状が出ている状態ですので、より長時間の装用は負担がかかります。
目の異常が発生するリスクも高くなりますので、短時間付ける楽しみ方をするのがおすすめです。
一般のカラコンだと8時間以上にならないようにした方がいいと言われていますので、乱視用のカラコンはそれより短くなるように意識するといいでしょう。
4時間から5時間を目安に付けるというのを徹底しておけば、乱視の人でも安全にカラコンを楽しむことができるのではないでしょうか。